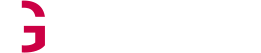ED以外の血管にまつわる疾患①
こんにちは。ギガクリニックです。
HPをご覧いただきありがとうございます。
EDは、血管に係わる疾患なのはご存じの通りですが、
ED以外の血管の疾患について紹介してみようと思います。
これから紹介する疾患の予防を意識することで、EDの症状の進行やED薬の効果をより実感しやすくなる場合もございますので参考にしてみて下さい。
1.心筋梗塞(心臓の血流が遮断されることにより心筋が損傷を受ける状態)
心筋梗塞は、心臓の血流が冠動脈による遮断などの影響で阻害され、心筋組織が酸素不足に陥る状態です。 これにより心筋が損傷を受け、心臓の機能が低下する可能性があります。心筋梗塞は不規則な生活習慣、高血圧、高コレステロール血症、喫煙などがリスクファクターとしての知られています。自覚症状としては急性胸痛、息切れ、吐き気、発汗などが現れることがあります。 症状には個人差があります。早期の診断と治療が重要で、治療により冠動脈の通りをよくし治療後は、リハビリや生活習慣の改善が必要となります。予防には、健康な食事、適度な運動、喫煙を避けるなどの対策が重要です。定期的な健康診断や医師のフォローアップを行い、再発を防ぐためにも積極的な対応が求められます。
2.脳卒中(脳の血流が遮断されることにより脳損傷が発生する病態)
脳卒中は、脳の血流が血管内で遮断されることにより、脳組織に酸素や栄養の供給が途絶え、脳細胞に損傷が生じている状態です。この状態は、脳梗塞(脳血管内の血栓によるもの)脳出血(脳血管の破裂によるもの)の2つの主要なタイプに分類されます。症状の表れ方は個人によって異なります。早期の診断と迅速な治療が必要で、特に脳梗塞の場合は血栓溶解療法や血管内治療が行われます。予防には、高血圧や高コレステロールの管理、喫煙を避け、健康的な食事と運動が推奨されます。 定期的な健康チェックやリスクファクターのチェックが、再発予防と早期発見に役立ちます。

3.血栓症(血液中の血栓が血管を詰まらせることにより発生する病気)
血栓症は、血液中に生じた血栓が血管内で詰まってしまう状態です。 血栓は、血液が凝固する際に形成される血小板と凝固因子の集合体であり、通常は傷口の修復や血栓症は様々な形態があり、深部静脈血栓症(下肢の深い静脈に形成される血栓)、肺塞栓症(肺動脈に血栓が詰まる)、心臓の血栓症などが一般的に見られます。
血栓症は、静脈内の血流が滞ったり、動脈内の血流が乱れたりすることでリスクが懸念されます。 運動不足、長時間の座位や寝たきり状態、妊娠、喫煙、高血圧、高脂血症等のリスクが軽減されています。血栓症は重篤な合併症として深部静脈血栓症が肺塞栓症が併発する可能性もあります。早期の診断と正しい治療が必要で、抗凝固療法や血栓溶解療法が一般的です。また血栓症の予防にはリスク因子の管理、適度な運動、体位変換などが重要です。 定期的な健康チェックと医師の指導により、血栓症の発症を防ぐことが求められます。
4.高血圧(血液の流れが制限されることにより血圧が上昇する病態)
高血圧は、血液の流れが血管の収縮性が制限されることにより血圧が持続的に上昇している状態です。 血液が通常よりも高い血圧で流れ込むため心臓や血管に負担がかかります。(蛇口をひねったホースの出口を指で押さえると遠くに水が飛ぶのと同じ原理です。)
2つのタイプがあり、一次性高血圧(特定の原因がない早期性高血圧)と二次性高血圧(他の疾患が原因で警戒される高血圧)があります。高血圧はしばしば無症状であり、未治療のままだと心臓疾患、脳卒中、腎臓障害などの重篤な合併症を考慮してリスクが考えられます。遺伝による影響、肥満、不健康な食事、運動不足、ストレス、喫煙などが高血圧のリスクとして挙げられます。高血圧をコントロールするためには、ライフスタイルの改善(バランスの取れた食事、運動、喫煙を避ける)、ストレス管理、減塩、アルコールの適量摂取などが重要です。必要に応じて薬物治療も行われます定期的な健康チェックと医師のフォローアップが、高血圧の早期発見と予防に役立ちます。健康な血圧を維持することは、心血管系の健康を守るために準備しています。

5.狭心症(冠動脈の血流が不足、心臓に酸素が足りない病態)
狭心症は、冠動脈の血流が不足し、心筋に必要な酸素が十分に供給されない状態、冠動脈狭窄により血流が制限されます。冠動脈の狭さは、主に冠動脈粥状硬化によります。これは動脈内に脂質やカルシウム(石灰化)が固着し血管が狭い状態で、高血圧、高脂血症、喫煙、糖尿病、運動不足などがリスク要因とされています。
狭心症の主な症状は時に胸痛で、階段を昇ったり坂道を登ったりした時など身体に負担がかかる運動したりして発生する安定狭心症(身体動作に伴うので労作性狭心症とも)と、活動時や負荷の強弱、安静時などに関わらず起こる不安定狭心症があります。
早期の診断と治療が重要で、症状や心電図、冠動脈造影などをもとに診断が行われます。治療法には薬物療法、血栓溶解療法、または冠動脈バイパス手術などがあります。食生活の改善や決められた薬剤の服用、禁煙やストレスの回避など、早期の治療と予防対策により、狭心症による重篤な合併症を防ぐことが重要です。
日常でできる血管の健康習慣
まだ続きはあるのですが、前半の終わりに、血管の健康を維持するためによいと言われている食事の摂り方についてもいくつか取り上げてみたいと思います。
1.動物性脂肪の摂りすぎに注意する。
コレステロールの上昇に注意。牛肉や豚肉など種類を問わず脂身や調理時に出る脂、サラダオイルなどの使用を少なくし日常的な動物性脂肪の摂取量を減らしてみましょう。
2.タンパク質の意識的な摂取
魚類、脂肪の少ない肉、大豆などの豆やそれを加工した食品なに良質なたんぱく質が含まれていると言われています。それらの摂取が難しい場合にはコンビニに売っているサラダチキンなども代替的なたんぱく源として選択してみてもよいでしょう。
3.アルコールは、ほどほどに
アルコールの摂取も動脈硬化のリスクを上げることが分かっています。注意するのは飲みすぎと一緒に食べる食べ物についてです。どうしてもビールなどには動物性の脂が多いものや塩分が多いものを合わせがちですが、それらはほどほどにし枝豆や脂肪分を落とした肉や魚、カルパッチョなどサラダも一緒に摂れる食事を心がけましょう。
ギガクリニック各院のご紹介
- 札幌院
- クリニック紹介
- アクセス
- 仙台院
- クリニック紹介
- アクセス
- 新宿南口院
- クリニック紹介
- アクセス
- 池袋院
- クリニック紹介
- アクセス
- 上野院
- クリニック紹介
- アクセス
- 新橋院
- クリニック紹介
- アクセス
- 東京院
- クリニック紹介
- アクセス
- 横浜院
- クリニック紹介
- アクセス
- 大宮院
- クリニック紹介
- アクセス
- 名古屋院
- クリニック紹介
- アクセス
- 栄院
- クリニック紹介
- アクセス
- UN金沢院
- クリニック紹介
- アクセス
- 梅田院
- クリニック紹介
- アクセス
- なんば院
- クリニック紹介
- アクセス
- 天王寺院
- クリニック紹介
- アクセス
- 京都院
- クリニック紹介
- アクセス
- 岡山院
- クリニック紹介
- アクセス
- 広島院
- クリニック紹介
- アクセス
- 博多院
- クリニック紹介
- アクセス
記事監修

総院長菅原 俊勝
- 2004年(平成16年)
- 秋田大学医学部医学科卒業
- 2014年(平成16年)
- ユナイテッドクリニック池袋院
- 2021年(令和3年)
- 医療法人社団 淳康会 高森会 理事就任
- 2021年(令和3年)
- 大宮院管理医師、総院長就任