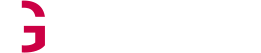EDとは? EDの原因と対処法を男性のお悩み特化【ギガクリニック】専門医が解説
人知れず男性が抱えている悩みの一つにEDがあります。長く悩まれている方はもちろん、勃起は心理的な影響が出やすい反応ですから、多くの男性が突発的に「ED?!」と不安に思われた瞬間を経験されています。また、将来的なEDでの不安を漠然と抱えていらっしゃる方もいます。EDに関する情報は様々公開されていますが、男性のお悩みに特化したギガクリニックの専門医が、EDに関する正しい知識と対処法を解説していきます。

💡この記事では下記の情報を得ることができます
| ✓ EDの正しい定義と理解 ✓ EDの主な原因 ✓ EDセルフチェック ✓ EDに対して自力で対処する対処法 ✓ その他クリニックなどで受けられる治療法 |
EDとは?
ED(イーディー)は英語の「勃起不全(Erectile Dysfunction)」の略称です。いわゆる「勃たない」という勃起状態に至らない状態の他
- 勃起するまでに時間がかかる
- 勃起の持続時間が短い
- 性交渉の途中で萎えてしまったり(中折れ)、十分な硬さが得らない
なども包括的に含め、満足な性行為を行えない状態として定義されています。勃起不全と聞くと「全く立たないこと」をイメージされがちですが、勃起を維持し続けられない状態(中折れ)もEDに含まれ、自慰行為の際には問題がなくとも、性行為の際に勃起が起きないというケースもあります。
この悩みは決して珍しいものではなく、日本性機能学会が2023年に調査したところ、20歳から79歳の日本人男性のうち、ED有病率は30.9%にのぼることが分かりました。これは日本人男性の人口にあてはめると約1,400万人の男性がEDで悩んでいる計算になり、ご自身が思っている以上に同じような悩みを抱えている人は周りにもたくさんいるのが実情です。 ギガクリニック全体では延べ100万人以上の治療実績がございますが、その中でも多くの方が「もしかしてEDかも」という不安を抱えて来院されます。
性の問題はなかなか他人に相談できず、一人で悩んでしまいがちですが、EDは放置してしまうと症状が重くなってしまう可能性があり、進行性の病気であるとも言われています。 また、EDは加齢だけではなく、生活習慣病や高血圧などの疾患の前兆や、一種の症状として起きる可能性もあります。アレ?と思ったら、まずはご自身の状態を知ることが大切です。
あなたのEDの原因は何なのか、どのように克服すれば良いのか、男性の悩みを専門にするギガクリニックが詳しく解説していきます。現在悩んでいる方はEDの治し方について、そしてまだの方もEDを予防するための対策について一緒に考えてみましょう。
ED(勃起不全)の原因
EDの原因は一つではありません。いくつかの種類に分類され、それぞれ特徴が異なりますが、ギガクリニックに来院される方も、複数の要因が絡み合って発症していることがほとんどです。どんな理由でEDになってしまうのか、それぞれの原因を理解することで、より効果的な改善策が見つけやすくなります。
器質性ED(身体的な原因)
身体の病気や、血管・神経の障害などが原因で起こるEDです。特に40歳以上の中高年層に多く見られます。
【特徴】
- 40歳以上の中高年層に多く見られる傾向がある
- 早朝勃起(朝立ち)が減少する、または見られないことが多い
- マスターベーション(自慰行為)の際にも勃起が困難な場合が多い
- 病気や障害の進行と共に徐々にEDが進行することが多い(例:動脈硬化の進行とともに悪化するなど)
- 前立腺がんの手術や、脊髄損傷などの術後に現れることがあり
【主な原因】
- 生活習慣病(糖尿病・高血圧): 糖尿病や高血圧は「動脈硬化」を進行させ、血流を悪化させます。陰茎の血管は非常に細いため、動脈硬化の影響を真っ先に受けやすく、勃起に必要な血液が十分に流れ込まなくなることでEDを引き起こします。
- 心疾患: 動脈硬化が原因となる「虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)」はEDと深く関連しています。
- 神経の障害: 前立腺がんの手術による勃起神経の損傷や、脊髄損傷、脳卒中などによって神経に障害が起こると、脳からの勃起の指令が陰茎に伝わりにくくなります。
心因性ED(精神的な原因)
精神的・心理的なストレスやトラウマが原因で起こるEDです。年齢に関係なく起こりますが、特に若年層から中年層に多く見られます。
【特徴】
- 比較的、突然発症することが多い
- 若年層に多く見られる傾向
- 性的興奮と勃起が一致しにくい
- 急な不安感を感じ、行為の途中で萎えてしまう(中折れ)
- 状況依存性が高く、状況によって症状が異なることが多い
- 特定の状況(例:パートナーとの性行為)でのみ勃起しない
- マスターベーションでは問題なく勃起できたり、早朝勃起(朝立ち)は見られる、といったケースが多い
【主な原因】
- パートナーとの関係悪化の他、パートナーに対して罪悪感や不信感を抱いているとEDになることがあります。
- 仕事のプレッシャーなど日常生活におけるストレスがEDを引き起こすことがあります。
- うつ病や不安障害などの精神疾患が影響しているケースもありますが、この場合治療薬による影響の可能性もあります。
- 過去の性行為での失敗体験、「次も失敗したらどうしよう」という強い不安(予期不安)やプレッシャーもEDを引き起こします。
- 幼少期の体験や性に対する強い嫌悪感や罪悪感など深層心理がトラウマになっているケースもあります。
混合性ED(身体・精神の複合)
上記の「器質性ED」と「心因性ED」の両方の原因が重なり合って起こるEDです。EDを発症している方の中で最も多いタイプとされています。
【特徴】
- ED患者の中で最も多いタイプ
- 特に中高年層に多く見られる
- 勃起の状態が日や状況によって不安定になりがち
【主な原因】
- 「器質性 → 心因性」の悪循環パターンが最も一般的で、加齢や生活習慣病で少し勃起しにくくなった(器質性)ところに、「また失敗するかもしれない」という不安(心因性)が加わることで、症状がさらに悪化するようなケースが典型的です。
- 逆に、長期間のストレス状態から不健康な生活習慣が定着しEDになることもあり、これは「心因性 → 器質性」のパターンもあります。
薬剤性ED(薬の副作用)
服用している薬の副作用によって引き起こされるEDです。服用を停止するとED症状はなくなりますが、自己判断での服用中止は大変危険です。必ず医師に相談して処方を変えてもらうなど調整してください。
【原因となりうる主な薬剤】
- 降圧剤(高血圧の治療薬の一部)
- 精神神経用剤(抗うつ薬、抗不安薬など)
- ホルモン剤(前立腺がん、前立腺肥大症の治療薬など)
加齢性ED
加齢に伴う身体機能の変化によって起こるEDです。40~50代の2人に1人は加齢性EDを発症しているというデータもあります。多くの場合、血管の老化などが関わるため「器質性ED」の一種として分類されます。
【特徴】
- 勃起時の硬さが依然と比較して不十分に感じるようになる
- 勃起を維持する時間や性行為中の中折れが増える
- 勃起までに時間を要し反応が鈍くなったと感じる
- 朝立ちが減る
- 急な発症ではなくゆっくりとした進行
【主な原因】
- 血管の老化(動脈硬化の進行)
- 男性ホルモン(テストステロン)の減少
- 神経機能の低下(性的刺激の伝達が鈍くなる)
ED(勃起不全)セルフチェックリスト
ご自身の状態を知るための目安としてください。1つでも当てはまる場合は、EDの可能性があります。
【勃起の状態について】
□ 性的欲求や興奮はあっても、勃起しない時がある
□ 勃起はするが、性行為を行うのに十分な硬さにならないと感じる
□ 勃起をしても、性行為の最後まで維持できないことがある(中折れ)
□ 朝立ち(早朝勃起)の回数が減った、または全くなくなった
□ 以前と比べて、勃起するまでに時間がかかるようになった
【性行為や心理面について】
□ 性行為の途中で、また萎えてしまうのではないかと不安になる
□ パートナーを満足させられるか、勃起に関して自信が持てない
□ 勃起しないことへの不安から、性行為自体を避けるようになった
【生活習慣や健康状態について】
□ 糖尿病、高血圧、脂質異常症(高コレステロールなど)を指摘されたことがある、または治療中である
□ 肥満気味(BMIが25以上)である
□ 喫煙の習慣がある
□ 定期的な運動習慣がない
チェックリストで多数が当てはまり、自主的な改善策を試しても効果が見られない場合や、より早期の改善を望む場合は、専門の医療機関での治療が有効な選択肢です。
EDは完治するのか
ED(勃起不全)の治療を検討される方から、「EDは完治するのか?」というご質問をよくいただきますが、治療以降の人生で勃起不全症が「完全に消え去る」ことは難しいとされています。もちろん、治療によって症状が「一過性に改善」することは十分に可能です。例えば20代で患った心因性EDが改善されるなどの事例は多数存在しています。ただ同一の男性が40代や50代になった時に、加齢性EDを発症する可能性は低くないためです。
EDを人生から「完治」させることは難しい一方で、近年の研究では、治療による「根本的な改善」の可能性も報告されています。ギガクリニックでも取り扱いのあるバイアグラ、レビトラ、シアリスなどのED治療薬(PDE5阻害薬)の使用は、血液中の「内皮前駆細胞」が増加することがわかっています。 この「内皮前駆細胞」は、血管の再生を促すなどの可能性が示唆されており、これによってEDの大きな原因である「血流障害(血管の老化・損傷)」に対して、根本的な治療(血管の修復)ができる可能性があると期待されています。今後さらに研究が進めば、対症療法(一時的な勃起補助)としてだけでなく、活用されていく可能性もあります。
自力でできる!ED対策・改善法第
「自分でEDに対してできることはあるの?」と思われた方に向けて、EDの対策方法についても解説していきます。EDは生活習慣と密接に関連しているため、ご自身で取り組める予防・改善策も多くあります。
- 食事の見直し
- 定期的な運動
- 禁煙・節酒
- 良質な睡眠
まずは、ご自身の生活習慣を見直すことから始めてみましょう。
食事の見直し
- 減塩 : 高血圧予防のため、塩分摂取を控えめに。カリウム(野菜、果物など)を摂り、塩分排出を促すことも有効です。
- バランスの良い食事 : 「タンパク質」「脂質」「炭水化物」のバランス(PFCバランス)を意識しましょう。特にタンパク質は不足しがちなため、ささみや豆腐、納豆などがおすすめです。
- 亜鉛の摂取 : 亜鉛はテストステロン(男性ホルモン)の維持に関わり、不足すると勃起機能に影響することがあります。牡蠣、赤身肉、レバー、ナッツ類などに多く含まれます。
定期的な運動
運動不足はEDのリスク要因です。ウォーキングや水泳などの「有酸素運動」(息が弾む程度を週2~5回)や、下半身を中心とした「筋力トレーニング」(週2~3回)が推奨されます。定期的な運動は血流を改善し、生活習慣病の予防にもつながります。
禁煙・節酒
喫煙は陰茎の血管に悪影響を与え、EDのリスクを高めます(喫煙本数が多いほどリスク上昇)。禁煙はEDリスクを減らすために重要です。また、過度な飲酒は高血圧や糖尿病など、EDの原因となる疾患を引き起こすため、適量を守りましょう。
睡眠
睡眠不足は、男性機能に関わるホルモンの分泌量を低下させる原因となります。朝起きたら光を浴びる、日中は適度に運動するなど、体内リズムを整え、良質な睡眠を心がけましょう。
クリニックによるED治療の種類
クリニックでのED治療は、原因疾患の治療、薬物療法、心理的なサポートなどが中心となります。この中でも主流となる治療方法は薬物療法です。
薬物療法によるED治療
ED治療薬は、陰茎への血流を増やし、勃起を補助してくれる薬剤です。生活習慣の見直しや原因疾患の治療と並行して服用することで、性行為への自信を取り戻し、心因性の改善にもつながります。
ギガクリニックで取り扱っている主なED治療薬には、以下のような種類があります。
- バイアグラ(シルデナフィル): 知名度が高く、しっかりとした硬さが特徴です。
- レビトラ(バルデナフィル): 効果発現が比較的早く、バイアグラと同等の硬さが期待できます。
- シアリス(タダラフィル): 効果時間が30時間以上と非常に長く、自然なタイミングでの性行為を望む方に適しています。
- ステンドラ(アバナフィル): 効果発現までの時間が非常に早いのが特徴です。
- ザイデナ(ウデナフィル): 効果発現が早く、効果時間も12時間以上と長いのが特徴です。
これらのお薬には、ほてり、頭痛、鼻詰まりなどの副作用が出ることがあります。また、持病や服用中の他のお薬(特に心臓病の薬など)によってはED治療薬を服用できない場合があります。必ず医師の診察を受けて処方してもらう必要があります。依存性はありませんので、ご安心ください。
原因疾患の治療
EDは、高血圧、糖尿病、心疾患、うつ病などのサインである場合があります。これらの原因となっている病気の治療を優先して行うことで、EDの症状が改善することもあります。
カウンセリングによる心理的サポート
心因性のEDの方や、失敗体験による不安が強い方は、専門家によるカウンセリングや認知行動療法が有効な場合があります。パートナーに悩みを打ち明け、理解と協力を求めることも、不安を軽減する上で大切です。
まとめ
ED(勃起不全)は、多くの男性が抱える共通の悩みであり、決して恥ずかしいことではありません。原因は、血管や神経の問題である「器質性」、精神的なストレスや不安による「心因性」、あるいは両方が組み合わさった「混合性」などさまざまです。
EDは生活習慣病と密接に関連しており、全身の健康状態を示すバロメーターとも言えます。まずはご自身で食事の見直し、運動、禁煙・節酒、良質な睡眠など、できることから始めてみましょう。
ご自身での解消に取り組んだ結果、満足のいく状態に至らなかったり、早期な改善を希望される場合には、ED治療薬の服用を検討するのも有効な手段です。実際に薬を使用して自信を取り戻した方もたくさんおり、医師の処方の元、用法用量を守って服用すれば安全に利用できます。
注意
薬のネット通販(個人輸入代行)サイトなども存在しますが、大変危険です。そのようなサイトで購入する薬の多くに偽物だったり異物が混入していたなどの問題が発生しています。製薬会社の調査結果では約60%の薬が偽造品だったというデータも存在しています。薬の効果がないだけではなく、健康被害の恐れもあります。 インターネットでの口コミや感想などを鵜呑みにせず、必ず医師へ相談を行ってから服用してください。
ギガクリニックでは各種ED治療薬の取り扱いもあり、EDで悩む多くの患者さんの診察を行ってきました。悩みを一人で抱え込まず、医師と一緒に改善に向けて取り組んでいきましょう。
EDに関するFAQ
セックスの途中で急にふにゃふにゃになってしまうのですが、これもEDですか?
はい。途中で萎えてしまう(中折れ)など、満足な性行為を行えない場合はEDと言えます。一人で悩まずに医師に相談してみましょう。
太りだしてからなんか立ちが悪くなったかも?
肥満や、それに伴う糖尿病などもEDの大きな原因です。根本改善として、食生活の見直しや適度な運動を推奨いたします。
行為には問題ないが、朝立ちする回数が減ってきた気がする。
朝立ちの回数が減ることは、EDの予兆(サイン)とも言えます。健康上の問題や、ストレスなど原因となるようなことはないか、確認してみましょう。
性欲が薄くなってセックスの回数が減ってきたかもしれない。
性欲減退も、男性ホルモンの減少などが原因の可能性があります。ホルモン補充療法などの選択肢もありますので、医師に相談してみましょう。
妊活を頑張ろうと思っているのですが、自慰以外だとなかなかタイミングよく勃起しません。
自慰では問題なく勃起しているのであれば、心因性EDの可能性も考えられます。「立たせなければ……」というプレッシャーが原因となることもあり得ますので、リラックスすることが大切です。
70過ぎたあたりから立ちが悪くなってきたのですが、ED治療薬は使っても平気ですか?
年齢制限はありませんが、罹っている疾患や服用している薬剤によってはお出しできないこともあります。安全に使用するため、まずはクリニックで医師にご相談ください。
ギガクリニック各院のご紹介
- 札幌院
- クリニック紹介
- アクセス
- 仙台院
- クリニック紹介
- アクセス
- 新宿南口院
- クリニック紹介
- アクセス
- 池袋院
- クリニック紹介
- アクセス
- 上野院
- クリニック紹介
- アクセス
- 新橋院
- クリニック紹介
- アクセス
- 東京院
- クリニック紹介
- アクセス
- 横浜院
- クリニック紹介
- アクセス
- 大宮院
- クリニック紹介
- アクセス
- 名古屋院
- クリニック紹介
- アクセス
- 栄院
- クリニック紹介
- アクセス
- UN金沢院
- クリニック紹介
- アクセス
- 梅田院
- クリニック紹介
- アクセス
- なんば院
- クリニック紹介
- アクセス
- 天王寺院
- クリニック紹介
- アクセス
- 京都院
- クリニック紹介
- アクセス
- 岡山院
- クリニック紹介
- アクセス
- 広島院
- クリニック紹介
- アクセス
- 博多院
- クリニック紹介
- アクセス
記事監修

総院長菅原 俊勝
- 2004年(平成16年)
- 秋田大学医学部医学科卒業
- 2014年(平成16年)
- ユナイテッドクリニック池袋院
- 2021年(令和3年)
- 医療法人社団 淳康会 高森会 理事就任
- 2021年(令和3年)
- 大宮院管理医師、総院長就任